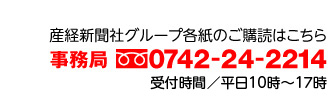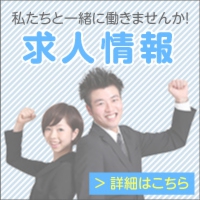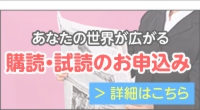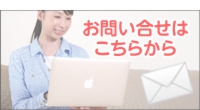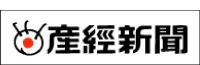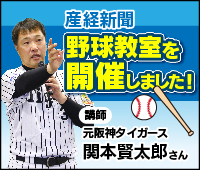正倉院宝物に未確認の染め技法 トルファンの古墳出土品と共通性
正倉院宝物の「茶地花樹鳳凰文﨟纈絁」=写真(正倉院紀要第43号から)=に施された文様が、名称にある「﨟纈」(ロウケツ染め)ではなく、これまで未確認の技法によるものであることが宮内庁正倉院事務所(奈良市)による調査で分かった。アルカリ性物質を含む剤が使われた可能性が高く、同様の痕跡はシルクロード都市だった中国新疆ウイグル自治区・トルファンの古墳群出土品で確認されている。
茶地花樹鳳凰文﨟纈絁(縦30・8㌢、横42・3㌢)は、江戸時代に屏風に貼り交ぜられた染織古裂のうちの一片。8世紀のものと考えられ、赤味を帯びた茶色地に花樹と鳳凰の文様が染め抜かれている。
これまでは溶かした蝋を防染に用いて文様を染め分けるロウケツ染めの技法が用いられたと考えられてきたが、他の宝物にあるロウケツ染めの特徴が見られないため今回、詳細に調査。この結果、糸の状態からみて、文様部分を抜き表すために何らかのアルカリ性物質を含む剤が使われた可能性が浮上。トルファンのアスターナ古墳群の出土品と共通性が見出せるという。
大陸から国内に持ち込まれたものか、国内で製作されたものかなどについては分からないが、同事務所保存課整理室員の片岡真純さんは紀要で「古代における文様染め技法の多様性の一端を示している」としている。