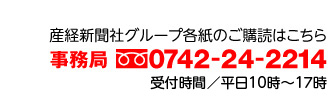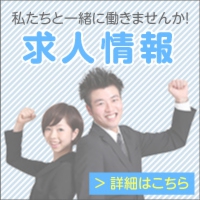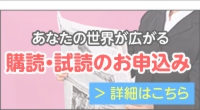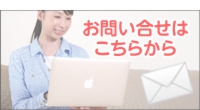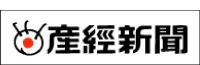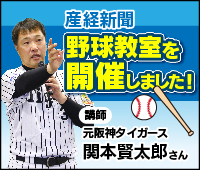藤原京にも外国人が住んでいた? 水洗トイレ遺構を調査、橿考研
2022年02月1日 産経新聞奈良支局 最新ニュース

調査で見つかった遺構。「奇妙な細長い穴」とある部分が水洗トイレ(アトリウム展の展示資料から)
わが国初の都城・藤原京(694~710年)の時代に、京内に外国人が住んでいた可能性があることが、発掘調査で見つかった水洗トイレの調査・研究から分かった。手掛かりは、豚肉や牛肉を加熱不十分な状態で食べたのが原因とみられる寄生虫の卵の痕跡。中国や朝鮮半島などの食習慣と一致する。
研究成果は橿原考古学研究所(橿原市)1階で3月18日まで開催中のアトリウム展「藤原京のお手洗い」(観覧無料)で、写真パネルや出土資料を使い紹介している。
水洗トイレの遺構は、平成30年、県営住宅の建て替えに伴う調査で、京の中心から北東約2㌔の桜井市西之宮で出土した。京内の水洗トイレ遺構としては8例目。
住宅の敷地内の地面に細長い穴(長さ7㍍以上、幅約1㍍、深さ約40㌢)を掘り、水が流れていた京の大路の側溝と2本の溝で接続。1本で敷地内に流水を引き入れ、汚水はもう1本で同じ側溝に流すように整備していたとみられる。
橿考研はこのトイレ跡で、大便に混じって体内から排出され、土の中に残る寄生虫卵を調査。その結果、豚肉や牛肉を加熱不十分な状態で食べて感染する有鉤・無鉤条虫卵を、京跡で初めて確認した。
外国の使節が滞在した鴻臚館跡(福岡市)や秋田城跡(秋田市)などではこのタイプの寄生虫卵が見つかっている。橿考研は水洗トイレがあった住宅にも中国や朝鮮半島などからの外国人がいた可能性があるとみている。