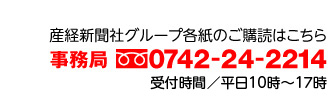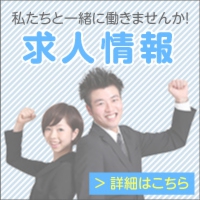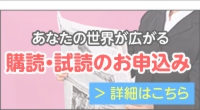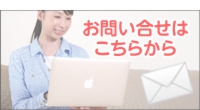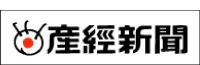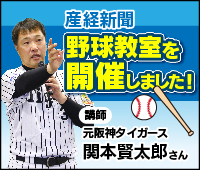行基供養の多宝塔 元文研が復元図
2023年04月17日 産経新聞奈良支局 最新ニュース

行基の供養堂とみられる円形建物跡の復元図案(元興寺文化財研究所提供)
奈良市の平城京跡西側の菅原遺跡から出土した奈良時代の高僧、行基(668~749年)の供養堂とみられる円形建物跡について、元興寺文化財研究所(元文研、奈良市)が復元図案を作成した。二重の多宝塔に似た形式で、「仏塔と廟所をあわせた塔廟としての多宝塔で、行基の供養堂としてふさわしい」としている。
元文研は宅地開発に伴い発掘調査を実施し、令和3年に円形建物跡などの発見を発表。丘陵地に柱穴が円形に並ぶ類例のない建物跡である上、約6㌔真東に東大寺が位置し、大仏造立に尽くした行基を供養するのにふさわしい立地から注目を集めた。
円形建物の復元案は12本の柱が円形に巡ってその外側に16本の柱が並ぶ構造で、檜皮葺きの屋根を持ち、上層の屋根は瓦葺きの方形を想定して作成。発掘調査報告書に掲載した。
多宝塔は平安時代初期の空海や最澄によるものが起源とされてきたが、報告書ではそれ以前に日本にもたらされた可能性があると指摘。鎌倉時代に行基の墓から掘り出された遺物には「多宝之塔」と記されていたとの記録もあることから、多宝塔は行基とつながりがあり「塔廟」だったとしている。
円形建物は行基が逝去した直後の749~760年頃に創建されたとみられ、行基ゆかりの四十九院の一つ、「長岡院」である可能性が高まったとしている。建物は9世紀初めに廃絶したとみられる。ただ、出土した瓦と同じ形の瓦が菅原寺(喜光寺)近くの室町時代の屋敷地井戸枠などに使われていたことから、行基が亡くなった同寺付近に移転していたことも考えられるという。
元文研の田辺征夫所長は「円形建物跡が建築史の研究者らの協力で復元できた意義は大きく、これをきっかけに議論が始まればいい。現地は残念ながら残らなかったが、奈良にはこのような貴重な遺構が埋もれていることに気づいてほしい」と話している。報告書は2千円。問い合わせは元興寺文化財研究所(0742・23・1376)。