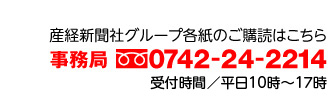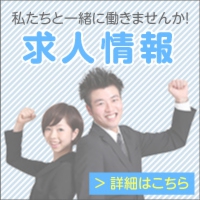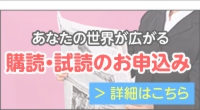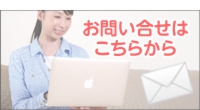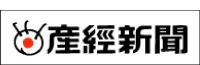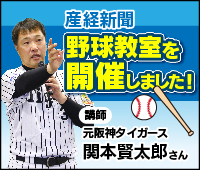石室は「片袖式」 6世紀後半の斑鳩町・舟塚古墳
2023年09月8日 産経新聞奈良支局 最新ニュース

大刀などが出土した舟塚古墳の玄室=斑鳩町法隆寺
斑鳩町法隆寺の円墳「舟塚古墳」の横穴式石室の構造や築造年代が分かり、発掘調査を担当した町教委と奈良大学が7日、発表した。石室は、被葬者を安置する玄室が通路・羨道から横に張り出した「片袖式」構造であることが判明。出土した須恵器から築造が6世紀後半であることも分かった。
舟塚古墳は現存する墳丘部が直径8・5㍍で、石垣で囲われている。今回、墳丘中央付近の約13平方㍍を発掘した。玄室は長さ3・8㍍、幅1・6㍍で、入り口(玄門)から見た正面の奥壁は5段以上の石材が積まれていた。石室内からは鉄製の大刀2点(いずれも長さ約1㍍)、馬具類3点、玉類12点、土器類37点が出土した。こうした状況から、被葬者は地域の有力者2人とみられる。
6世紀後半に築造された町内の古墳としては、豪華な金銅製馬具の副葬品で知られる藤ノ木古墳もあるが、舟塚古墳の方が古いとみられ、奈良大文学部の豊島直博教授(考古学)は「藤ノ木古墳以前の町内の古墳構造を知る重要な成果になった」と話している