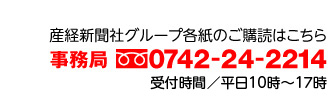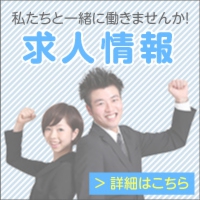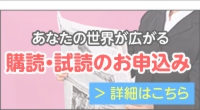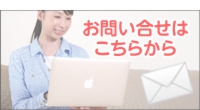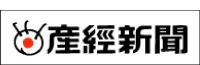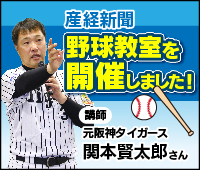初代法隆寺「若草伽藍」の南端か 瓦が大量廃棄された溝跡見つかる 斑鳩町
法隆寺境内(斑鳩町)の南側で、飛鳥時代に聖徳太子が創建した初代法隆寺だった「若草伽藍(がらん)」の南端の可能性が高い溝跡が同町教育委員会の発掘調査で見つかった。日本書紀で天智9(670)年に焼失したとされる初代法隆寺の実態を知る上で貴重な成果という。
若草伽藍は現在の金堂や五重塔がある西院伽藍の南東に位置し、塔や金堂が南北に並ぶ四天王寺式伽藍配置だったとされる。今回は塔跡南東で建物建設に伴い、456平方㍍を調査。塔跡などと並行する位置に幅約2㍍の溝跡が約16㍍にわたり出土した。
溝跡には7世紀の瓦が大量に廃棄されており、焼けた壁土片もあることから建物が火災で焼けた後にまとめて捨てられたとみられる。若草伽藍はこれまでに北側、西側で塀とみられる遺構が確認され、南北約170㍍、東西約150㍍と考えられていたが、今回の出土地は南北が約14㍍短くなる位置となっている。
廃棄された瓦片は数万点以上に上るといい、金堂に使われていた可能性がある鴟尾(しび)の破片も含まれていた。さらに、瓦質の板状表面に軒平瓦に使う文様のスタンプを押した類例のない品もあった。
法隆寺は聖徳太子が亡くなった父の31代用明天皇のために発願し、推古15(607)年頃に建立。天智9(670)年に焼失し、その後再建されたのが現在の西院伽藍とされる。
調査担当の荒木浩司・生涯学習課長補佐は「遺構は若草伽藍の範囲を考える上で一つの重要な資料になる」と話している。
現地説明会は3日午前10時~午後3時。