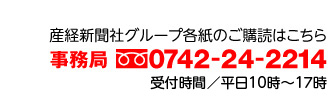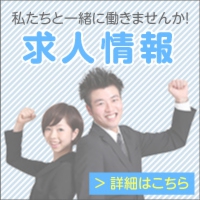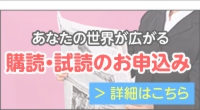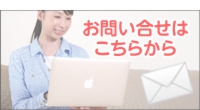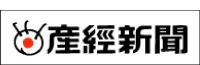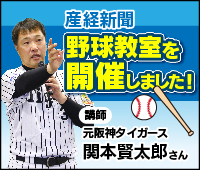古代の甘味料再現に挑戦 天理・福住中生、樹液採集し煮詰める
清少納言の「枕草子」に記された古代の甘味料「甘葛煎(あまづらせん)」の再現に、天理市立福住中学校の1、2年生が取り組んだ。出来上がった甘葛煎は今夏、学校でかき氷にかけて楽しむ予定。

ナツヅタの幹を上下に振って樹液を集める生徒ら=天理市
甘葛煎はナツヅタの樹液を煮詰めて作ったとされ、さっぱりとした甘みが特徴。平城京の長屋王邸跡から出土した木簡には「甘葛」という記載があり、約1300年前には存在したとされるが、砂糖が世に広まった江戸時代には姿を消したという。

樹液を煮詰める生徒たち
奈良女子大では平成年から甘葛煎の再現に挑み、令和5年には再現したシロップを開発した。今回、福住中の生徒13人が同大学協力研究員の前川佳代さん(57)の指導のもと、ナツヅタの幹を上下に振るなどして樹液を採集。その後、生徒たちは鍋に入れた樹液をかき混ぜながら根気強く強火で煮詰めた。
出来上がった甘葛煎を試食した生徒たちは「甘い」「おいしい」と声を上げていた。2年の中森翔太さん(14)は「甘さを手に入れる昔の人の労力を知った。頑張りに見合った甘さ。はちみつに比べるとさっぱりしている。ヨーグルトにも合いそう」と笑顔を見せた。
前川さんは「甘いものがあふれる現代と違って、1300年前は甘みは庶民には手に入らないものだった。そうした歴史を子供たちに知ってもらいたい」と話した。