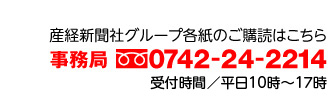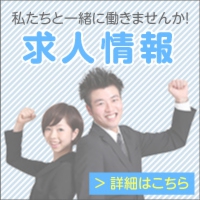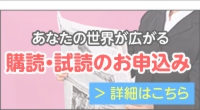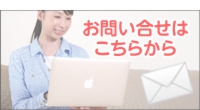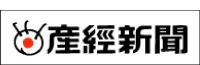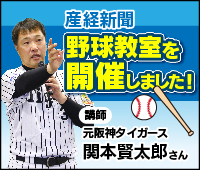県、日常規模の降雨でマップ作成 水害リスク把握 備えを HPで閲覧可能
土地利用や住宅を建てる際に生かしてもらおうと、県は大和川水系の「水害リスクマップ」を作成し、インターネットで公開を始めた。これまでの「洪水浸水想定区域図」は最大規模降雨を想定し迅速な避難につなげるのが主目的だったが、今回のマップは日常的に発生する規模の降雨で想定される浸水の範囲などを示し、リスク把握を重視している。
県が水防法に基づき公表してきた洪水浸水想定区域図は、想定最大規模の降雨で河川の堤防が壊れ、水が流れ出す最悪の事態を想定。避難の参考にするためには有効な一方、浸水の生じやすさについては把握が難しかった。
マップの対象は大和川水系の18河川で、浸水深(0・0㍍以上、0・5㍍以上、3・0㍍以上)ごとに浸水の発生を図示。日常的に起こりやすい規模の降雨の場合に想定される浸水の範囲や頻度を明確化している。頻度は1年間にその規模を超える洪水が発生する確率を10%(1時間雨量は52㍉)~0・5%(同84㍉)で色分けし、一目で分かるようになっている。
県内で近年の水害としては、平成29年10月に台風の影響により床上・床下浸水などの被害が多発した。
県河川整備課の担当者は「自分たちが住んでいる地域の水害リスクを知り、家を建てる際に考慮するなど、万が一に備えていただきたい」と話し、災害に強いまちづくり、企業立地などにも生かしてもらうことを期待している。
マップは同課のホームページから閲覧できる。紀の川水系と淀川水系のマップは完成次第公表する。