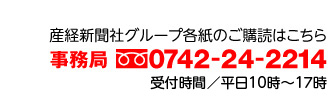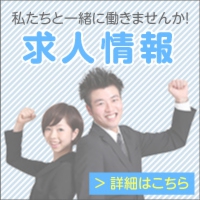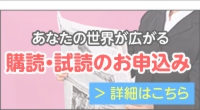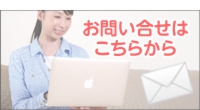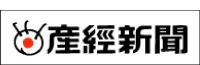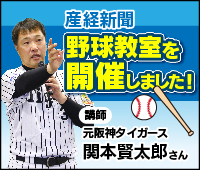クマ目撃増、生息域拡大 保護から管理へ 県が方針転換、殺処分も
県内で目撃情報が相次ぎ、生息域が拡大しているとみられるツキノワグマに対して県は、「保護重視から管理」に方針を転換することを明らかにした。クマの保護管理計画を改定し、集落内では殺処分も含めた対策とするとしている。

目撃情報が相次いでいるツキノワグマ(県提供)
奈良と三重、和歌山の3県にまたがる森林に生息する「紀伊半島のツキノワグマ」は、独自の遺伝的特性を持つことや生息数が少ないことから「絶滅のおそれのある地域個体群」として環境省のレッドリストに掲載され、保護されてきた。同省の平成4年調査では個体数は150頭だったが、令和6年度には395~560頭に増えていると推定されている。
県によると、県内での目撃情報も5年度は58件だったが、6年度は145件と大幅に増加。今年は5月以降、天理市や山添村、奈良市の東部山間で目撃情報が相次いでおり、従来は吉野川以南とされていた生息域が拡大しているとみられるという。
こうした中、県はクマに対する方針を転換。これまでは捕獲した場合は人里に対する恐怖心を学習させた上で山奥に放つ「学習放獣」を行ってきたが、改定案では出没場所を区分けして対応する。集落内や農地など人間活動が盛んな「集落ゾーン」では原則殺処分、「集落周辺ゾーン」では1回目は学習放獣し、2回目の捕獲となった場合は原則殺処分とする。「森林ゾーン」は原則殺処分は行わない。総捕獲数は県内推定生息数の8%以内とする。
県は今後、パブリックコメント(意見公募)を実施し、10月の施行を目指す。
県農業水産振興課の担当者は「これだけ目撃情報が増え、『怖いので何とかしてほしい』という声もあり、計画を見直すことになった」と話している。